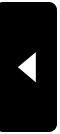3連休:最終日、“秋”満喫 /滋賀
3連休:最終日、“秋”満喫 /滋賀
3連休最終日の23日、県内は好天に恵まれ、各地で開かれたイベントは家族連れなどでにぎわった。
◇思い思いに「人型」作り--草津・創造館
草津市野路6のしが県民芸術創造館で23日、子どもたちに芸術に親しんでもらうイベント「みんなでつくろうアート☆キャラバン号」が開かれた。参加した小学生ら26人は、色紙で等身大の「人型」を作って楽しんだ。
子どもたちはまず、舞台上でピアニカや木琴、小太鼓などを合奏しながら、即興ダンスを体験。続いて、床に敷かれた5色の巨大なカッティングシートの上に思い思いのポーズで寝転がり、白色ペンで型取りをして、人型を切り取った。人型は、ワゴン車に張って飾り付けた。
同館は来年2月まで、このワゴン車を県内で走らせ芸術振興活動を繰り広げる。主なイベントは「サイオン・カマラ ワークショップ」(アフリカンダンス、来年1月10日)▽「未来へ」(室内楽、2月7日)▽「親子で楽しむアフリカのリズム」(2月予定)など。
問い合わせは同館(077・564・5815)。【後藤直義】
◇理解と交流深める祭り--野洲・にっこり作業所
障害者への地域の理解を深め、互いに交流しようと、野洲市辻町の野洲健康福祉センターで23日、「第26回にっこりまつり収穫祭」が催され、多くの市民が訪れた。
社会就労センター「にっこり作業所」(同市)が主催。NPO法人や企業などと協力し、毎秋恒例の祭りとして市民に定着している。会場には、地元の農家が持ち寄った新鮮な野菜や、ビワマスを使った炊き込みご飯などの郷土料理、約60店のフリーマーケットなどが並んだ。
同作業所の河副健一所長は「インフルエンザの影響で開催を悩んだが、『毎年楽しみにしている、ぜひ開催を』と多くの要望があった。天候にも恵まれ、今年も市民のみなさんと触れ合えてよかった」と笑顔だった。
続きはこちら・・・
3連休最終日の23日、県内は好天に恵まれ、各地で開かれたイベントは家族連れなどでにぎわった。
◇思い思いに「人型」作り--草津・創造館
草津市野路6のしが県民芸術創造館で23日、子どもたちに芸術に親しんでもらうイベント「みんなでつくろうアート☆キャラバン号」が開かれた。参加した小学生ら26人は、色紙で等身大の「人型」を作って楽しんだ。
子どもたちはまず、舞台上でピアニカや木琴、小太鼓などを合奏しながら、即興ダンスを体験。続いて、床に敷かれた5色の巨大なカッティングシートの上に思い思いのポーズで寝転がり、白色ペンで型取りをして、人型を切り取った。人型は、ワゴン車に張って飾り付けた。
同館は来年2月まで、このワゴン車を県内で走らせ芸術振興活動を繰り広げる。主なイベントは「サイオン・カマラ ワークショップ」(アフリカンダンス、来年1月10日)▽「未来へ」(室内楽、2月7日)▽「親子で楽しむアフリカのリズム」(2月予定)など。
問い合わせは同館(077・564・5815)。【後藤直義】
◇理解と交流深める祭り--野洲・にっこり作業所
障害者への地域の理解を深め、互いに交流しようと、野洲市辻町の野洲健康福祉センターで23日、「第26回にっこりまつり収穫祭」が催され、多くの市民が訪れた。
社会就労センター「にっこり作業所」(同市)が主催。NPO法人や企業などと協力し、毎秋恒例の祭りとして市民に定着している。会場には、地元の農家が持ち寄った新鮮な野菜や、ビワマスを使った炊き込みご飯などの郷土料理、約60店のフリーマーケットなどが並んだ。
同作業所の河副健一所長は「インフルエンザの影響で開催を悩んだが、『毎年楽しみにしている、ぜひ開催を』と多くの要望があった。天候にも恵まれ、今年も市民のみなさんと触れ合えてよかった」と笑顔だった。
続きはこちら・・・
タグ :障害福祉
馬のゼッケン、バッグに変身! 人気集める 滋賀・栗東トレセン
馬のゼッケン、バッグに変身! 人気集める 滋賀・栗東トレセン
【滋賀】日本中央競馬会(JRA)の栗東トレーニングセンター(栗東市)の競走馬が使用した帆布ゼッケンを、県内の障害者施設がバッグのブランドに変身させた。名前は「優駿」を意味する「steed」。06年に限定販売した試作品が競馬ファンに好評だったため、デザイナーの協力を得て品質を高めた。インターネット販売が中心で、若い女性からも「可愛くて使いやすい」と人気を集めているという。【安部拓輝】
◇JRAトレセンと福祉施設がコラボ
栗東トレセンはJRA初の調教場として1969(昭和44)年に設立され、オグリキャップやディープインパクトなどの名馬も育ててきた。従来、馬のゼッケンは流出して売買されるのを防ぐため廃棄していた。
施設の清掃作業で障害者らと一緒に出入りしていた県社会就労事業振興センターの城貴志さん(32)が再利用を発案してトレセンに持ち掛けたところ、「福祉のためなら」と快諾を得た。数百枚を無償で譲り受けてバッグを試作しホームページや阪神競馬場(兵庫県宝塚市)で販売すると引き合いが相次いだ。
今年に入って改良を加え、バッグ(税込み7500~9000円)、ウエストポーチ(同4000円)、セカンドバッグ(同3500円)の3種類を用意。栗東トレセンが開設40周年を迎えた今月からネット上で本格販売を始めた。
馬の汗や油で汚れたゼッケンは草津市内の若竹作業所で手洗いし、守山市の聴覚障害者施設「びわこみみの里」で縫製。帆布に縫い込まれた厩舎(きゅうしゃ)と馬番号は原型のまま、完成品には焼き印で製造番号を入れた。
続きはこちら・・・
【滋賀】日本中央競馬会(JRA)の栗東トレーニングセンター(栗東市)の競走馬が使用した帆布ゼッケンを、県内の障害者施設がバッグのブランドに変身させた。名前は「優駿」を意味する「steed」。06年に限定販売した試作品が競馬ファンに好評だったため、デザイナーの協力を得て品質を高めた。インターネット販売が中心で、若い女性からも「可愛くて使いやすい」と人気を集めているという。【安部拓輝】
◇JRAトレセンと福祉施設がコラボ
栗東トレセンはJRA初の調教場として1969(昭和44)年に設立され、オグリキャップやディープインパクトなどの名馬も育ててきた。従来、馬のゼッケンは流出して売買されるのを防ぐため廃棄していた。
施設の清掃作業で障害者らと一緒に出入りしていた県社会就労事業振興センターの城貴志さん(32)が再利用を発案してトレセンに持ち掛けたところ、「福祉のためなら」と快諾を得た。数百枚を無償で譲り受けてバッグを試作しホームページや阪神競馬場(兵庫県宝塚市)で販売すると引き合いが相次いだ。
今年に入って改良を加え、バッグ(税込み7500~9000円)、ウエストポーチ(同4000円)、セカンドバッグ(同3500円)の3種類を用意。栗東トレセンが開設40周年を迎えた今月からネット上で本格販売を始めた。
馬の汗や油で汚れたゼッケンは草津市内の若竹作業所で手洗いし、守山市の聴覚障害者施設「びわこみみの里」で縫製。帆布に縫い込まれた厩舎(きゅうしゃ)と馬番号は原型のまま、完成品には焼き印で製造番号を入れた。
続きはこちら・・・
タグ :障害者就労
信楽焼製の寅切符 信楽-貴生川間の往復乗車券
信楽高原鉄道:信楽焼製の寅切符 信楽-貴生川間の往復乗車券--甲賀 /滋賀
◇「くるみ作業所」が焼き上げ
甲賀市信楽町の信楽高原鉄道は来年の干支(えと)の寅(とら)を描いて焼き上げた信楽焼製切符(縦16・2センチ、横11・5センチ)の販売を始めた。信楽-貴生川間の往復乗車券として、大人、子ども各1人が利用できる。
地元の陶芸家、雲林院ユカリさんがデザインし、障害者が働く「信楽くるみ作業所」の利用者たちが焼き上げた。可愛らしい親子の虎が寄り添って歩く様子が描かれ、使用後は壁掛けにも使える。1枚1360円で2000枚用意。信楽駅とJR大津駅構内の近江鉄道バス案内所「おおつステーションセンター」で販売する。
問い合わせは同鉄道(0748・82・4366)。
続きはこちら・・・
◇「くるみ作業所」が焼き上げ
甲賀市信楽町の信楽高原鉄道は来年の干支(えと)の寅(とら)を描いて焼き上げた信楽焼製切符(縦16・2センチ、横11・5センチ)の販売を始めた。信楽-貴生川間の往復乗車券として、大人、子ども各1人が利用できる。
地元の陶芸家、雲林院ユカリさんがデザインし、障害者が働く「信楽くるみ作業所」の利用者たちが焼き上げた。可愛らしい親子の虎が寄り添って歩く様子が描かれ、使用後は壁掛けにも使える。1枚1360円で2000枚用意。信楽駅とJR大津駅構内の近江鉄道バス案内所「おおつステーションセンター」で販売する。
問い合わせは同鉄道(0748・82・4366)。
続きはこちら・・・
タグ :障害者就労
食べる・歩く「暗闇体験」見えてくるものは?
食べる・歩く「暗闇体験」見えてくるものは?
目隠しして食事をしたり、真っ暗な道を歩いたり。「暗闇」を体験する企画が静かな人気だ。視覚を閉ざすと、何が見えてくるのだろう。
東京・品川の商店街の会議室に14日、アイマスク姿の10人ほどの男女がテーブルを挟んで向き合った。照明を消し、窓にカーテンを引いて光を感じることすらできない。この環境で、ご飯を食べるのだ。
仏教を広める若手住職らのグループ「彼岸寺」が企画した、その名も「暗闇ごはん」。コトッと食器が置かれた音がすると、みんな一斉に手を伸ばす。皿か。おわんか。確認した参加者は、中の食べ物を指で突っつく。そこに「しょうゆを用意しました。お刺し身に使って下さい」とお坊さん。口にした人は「んっ、魚じゃない。コンニャクの刺し身?」と首をかしげた。
◆人間の感覚を取り戻す◆
食べ終えた江戸川区の保育士福田幸江さん(33)は「指先や舌の感覚が鋭くなり、丁寧にご飯を味わえた」と満足そう。保育園では小さな子供たちに付きっきりで、昼食は大急ぎ。夜も外食やコンビニの総菜が多い。「普段は忘れている人間としての感覚を取り戻せるのがうれしい」
記者もトライしてみたが、視界を閉ざされると、まず、触って確認したくなる。舌でころがし、ゆっくりかみ、次のお皿が運ばれてくる気配がすると、どんなにおいか追っていた。これが人間本来の感覚なのか。
「彼岸寺」メンバーの青江覚峰(かくほう)さん(32)は「食べ物に感謝し、自分自身や他人との対話を楽しみ、多忙な日常を見つめ直すきっかけにしてほしい」と語る。2008年から月1回ペースで始め、既に延べ約500人が参加。リピーターもいるという。
こうした企画はほかにもあり、滋賀県彦根市のNPO法人「五環生活」(近藤隆二郎代表)は2か月に1回、目隠しで野菜を味わう食事会を開催。東京・港区のホテルでは12月、アイマスクでコース料理を楽しむイベントが開かれる。
◆すり足で恐る恐る◆
渋谷区ではNPO法人の主催で、真っ暗な中をグループで歩く「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」(暗闇での対話)が3月から開かれている。ドイツで20年前、視覚障害者への理解を深めるため始まった企画だ。
場所はビルの地下。視覚障害を持つ案内人の「つえで足元を確認しましょう」という声を頼りに、すり足で恐る恐る進む。砂利や落ち葉を踏みしめる感触。木や草や土のにおい。進むにつれ、周囲の環境が変わるのが分かってきた。参加者同士が「木があるから気を付けて」「すみません、足を踏みました」と声を掛け合う。初対面なのになぜか親しみがわいた。
続きはこちら・・・
目隠しして食事をしたり、真っ暗な道を歩いたり。「暗闇」を体験する企画が静かな人気だ。視覚を閉ざすと、何が見えてくるのだろう。
東京・品川の商店街の会議室に14日、アイマスク姿の10人ほどの男女がテーブルを挟んで向き合った。照明を消し、窓にカーテンを引いて光を感じることすらできない。この環境で、ご飯を食べるのだ。
仏教を広める若手住職らのグループ「彼岸寺」が企画した、その名も「暗闇ごはん」。コトッと食器が置かれた音がすると、みんな一斉に手を伸ばす。皿か。おわんか。確認した参加者は、中の食べ物を指で突っつく。そこに「しょうゆを用意しました。お刺し身に使って下さい」とお坊さん。口にした人は「んっ、魚じゃない。コンニャクの刺し身?」と首をかしげた。
◆人間の感覚を取り戻す◆
食べ終えた江戸川区の保育士福田幸江さん(33)は「指先や舌の感覚が鋭くなり、丁寧にご飯を味わえた」と満足そう。保育園では小さな子供たちに付きっきりで、昼食は大急ぎ。夜も外食やコンビニの総菜が多い。「普段は忘れている人間としての感覚を取り戻せるのがうれしい」
記者もトライしてみたが、視界を閉ざされると、まず、触って確認したくなる。舌でころがし、ゆっくりかみ、次のお皿が運ばれてくる気配がすると、どんなにおいか追っていた。これが人間本来の感覚なのか。
「彼岸寺」メンバーの青江覚峰(かくほう)さん(32)は「食べ物に感謝し、自分自身や他人との対話を楽しみ、多忙な日常を見つめ直すきっかけにしてほしい」と語る。2008年から月1回ペースで始め、既に延べ約500人が参加。リピーターもいるという。
こうした企画はほかにもあり、滋賀県彦根市のNPO法人「五環生活」(近藤隆二郎代表)は2か月に1回、目隠しで野菜を味わう食事会を開催。東京・港区のホテルでは12月、アイマスクでコース料理を楽しむイベントが開かれる。
◆すり足で恐る恐る◆
渋谷区ではNPO法人の主催で、真っ暗な中をグループで歩く「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」(暗闇での対話)が3月から開かれている。ドイツで20年前、視覚障害者への理解を深めるため始まった企画だ。
場所はビルの地下。視覚障害を持つ案内人の「つえで足元を確認しましょう」という声を頼りに、すり足で恐る恐る進む。砂利や落ち葉を踏みしめる感触。木や草や土のにおい。進むにつれ、周囲の環境が変わるのが分かってきた。参加者同士が「木があるから気を付けて」「すみません、足を踏みました」と声を掛け合う。初対面なのになぜか親しみがわいた。
続きはこちら・・・
タグ :イベント
障害の有無を越えたアート展
障害の有無を越えたアート展
障害の有無の枠を超え、作品を通して互いの感性をたたえ合う「第17回陽(ひ)と風と……とっておきのアーティストたち」展が17日、福山市西町2丁目のふくやま美術館で始まった。同市水呑町の知的障害者施設「福山六方学園」などでつくる実行委が、岩手県から福岡県まで全国14の障害者施設などで活躍するアーティストらの作品を招待。障害者たちによる芸術活動「アウトサイダー・アート」の最新の展開と、その多様性を堪能できる。23日まで。(広津興一)
障害者による芸術はボーダレス・アートや、フランス語で「アール・ブリュット(生の芸術)」とも呼ばれ、その創造性豊かな作品に注目が集まっている。来年3月には、パリのアル・サン・ピエール美術館で、日本の障害者の作品を紹介する「アール・ブリュット・ジャポネ展」も開催。全国20都道府県から約60人の作品が出展され、その中に福山六方学園の2人も選ばれた。この開催を記念し、今回の「陽と風と……」展では全国の施設に参加を呼びかけ、50点が集まった。
愛らしい表情をした手のひらサイズの地蔵を何体もつくり続けるやまなみ工房(滋賀県)の山際正己さんや、平仮名の「も」を無数に書くことで、柔らかな陰影を持つデザイン画を描く工房集(埼玉県)の齋藤裕一さんらの作品のほか、ディズニーのキャラクターを文字とともに丁寧に縫い上げた刺繍(し・しゅう)、絵図から描き起こして内部まで細かく仕上げた電車のペーパークラフトなど、その表現世界は多彩だ。
続きはこちら・・・
障害の有無の枠を超え、作品を通して互いの感性をたたえ合う「第17回陽(ひ)と風と……とっておきのアーティストたち」展が17日、福山市西町2丁目のふくやま美術館で始まった。同市水呑町の知的障害者施設「福山六方学園」などでつくる実行委が、岩手県から福岡県まで全国14の障害者施設などで活躍するアーティストらの作品を招待。障害者たちによる芸術活動「アウトサイダー・アート」の最新の展開と、その多様性を堪能できる。23日まで。(広津興一)
障害者による芸術はボーダレス・アートや、フランス語で「アール・ブリュット(生の芸術)」とも呼ばれ、その創造性豊かな作品に注目が集まっている。来年3月には、パリのアル・サン・ピエール美術館で、日本の障害者の作品を紹介する「アール・ブリュット・ジャポネ展」も開催。全国20都道府県から約60人の作品が出展され、その中に福山六方学園の2人も選ばれた。この開催を記念し、今回の「陽と風と……」展では全国の施設に参加を呼びかけ、50点が集まった。
愛らしい表情をした手のひらサイズの地蔵を何体もつくり続けるやまなみ工房(滋賀県)の山際正己さんや、平仮名の「も」を無数に書くことで、柔らかな陰影を持つデザイン画を描く工房集(埼玉県)の齋藤裕一さんらの作品のほか、ディズニーのキャラクターを文字とともに丁寧に縫い上げた刺繍(し・しゅう)、絵図から描き起こして内部まで細かく仕上げた電車のペーパークラフトなど、その表現世界は多彩だ。
続きはこちら・・・
タグ :障害福祉